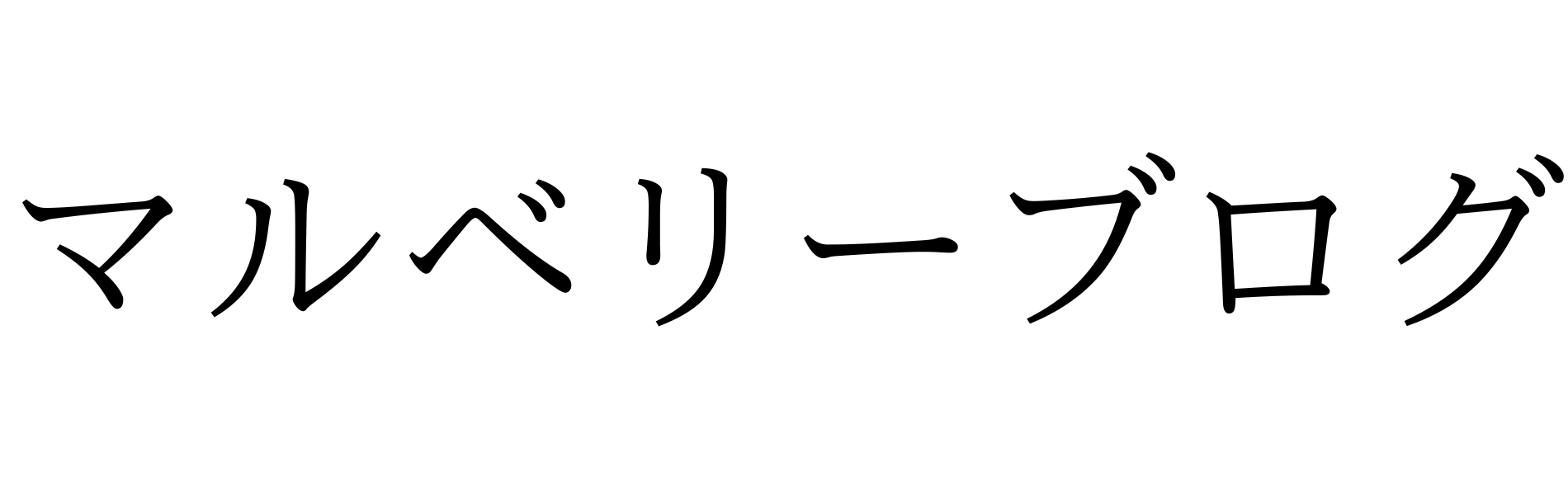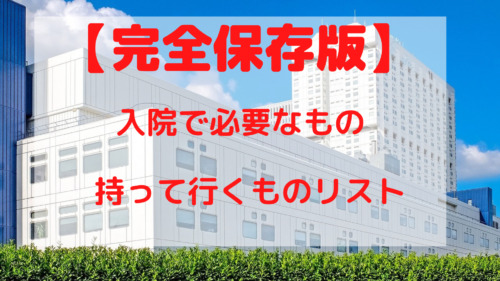なんで不安?原因を知ろう
- 未知へのコワさ: 何が起こるか分からないと、ドキドキしちゃうよね。
- 痛いのヤダ!: 手術後の痛みがどれくらいか、すごく心配…。
- 体、変わっちゃう?: 傷跡とか、元の生活に戻れるか不安だなぁ。
- もしも…の心配: うまくいかなかったら?って考えちゃう。
手術の違いって?
- 開腹手術: お腹を少し大きく切るよ。しっかり見て治す!
- 腹腔鏡手術: 小さな穴からカメラで見るよ。傷が小さいのが◎
- 選び方: 病気や体に合わせて、先生がベストな方法を選ぶよ!
不安解消!7つのステップ
- ①知る: まずは正しい情報を集めよう!病院の資料が安心だよ。
- ②イメージ: 手術や回復を具体的に想像!前向きな気持ちに。
- ③リラックス: 深呼吸や好きな音楽でホッと一息。気分転換も大事。
- ④話す: 不安な気持ち、誰かに話してみよう。話すと楽になるよ。
- ⑤準備: 入院の準備や家のこと。やることやると安心感がUP!
- ⑥体調管理: ご飯しっかり、睡眠たっぷり。元気な体で臨もう!
- ⑦未来を見る: 手術は元気になるため!楽しい未来を考えよう!
痛み、どうなるの?
- 対策バッチリ: 点滴や飲み薬で、痛みはしっかり和らげられるよ!
- 我慢はNG!: 痛かったらすぐ教えてね。それが回復への近道。
- 専門家がいる: 麻酔の先生が、手術中も後も見ててくれるから安心。
まわりの力を借りよう
- 正直に伝える: 不安な気持ちや、手伝ってほしい事を話してみて。
- 具体的に頼む: 「これお願い!」って具体的に言うと、相手も助けやすいよ。
- 「ありがとう」を忘れずに: 感謝の気持ちが、良い関係を作るカギ🔑
この記事では、開腹手術や腹腔鏡手術を控えたあなたの「どうしようもない不安」を具体的な「安心」に変える方法を徹底解説します。
手術が決まったものの、夜も眠れないほど心配…。「痛かったらどうしよう」「ちゃんと元に戻れるかな」
 初心者
初心者その気持ち、痛いほどよく分かります。
大きな手術を前に、不安を感じるのはごく自然な反応です。
でも、実はその不安、少しの知識と準備で驚くほど軽くなるって知っていましたか?
多くの人が手術前に感じる不安は、「何が起こるかわからない」という未知への恐怖が大きな原因。
逆に言えば、手術のこと、痛み対策のこと、回復のことを具体的に知れば、漠然とした不安は「対処可能な課題」に変わるんです。



手術は決して「怖いだけ」のものではありません。
あなたの健康を取り戻し、より良い未来へ進むための大切なステップなのです。
この記事を読み終えるころには、「怖い」という気持ちが「よし、しっかり準備して臨もう!」という前向きな気持ちに変わっているはず。
さあ、一緒に不安を安心に変える一歩を踏み出しましょう!
この記事が、あなたの手術への道のりを少しでも明るく照らす灯りとなることを願っています。
なぜ手術前に不安になるの?原因を理解して向き合おう
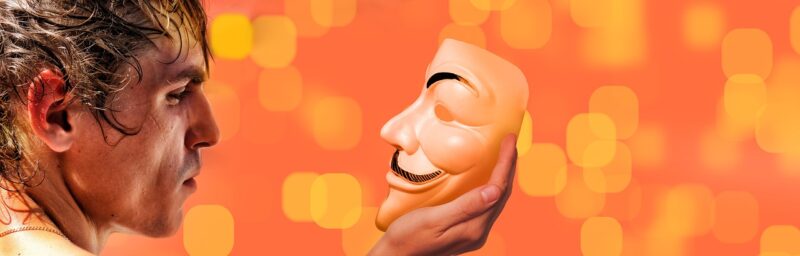
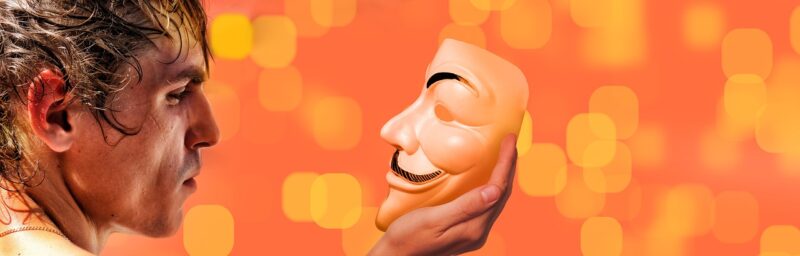
手術前に不安を感じるのは、あなただけではありません。
多くの人が同じように、さまざまな心配事を抱えています。
その不安の正体を知ることから、解消への第一歩が始まりますよ。
まず、「未知への恐怖」が大きいですね。
手術室という特別な空間で、麻酔で意識がなくなり、自分の体にメスが入る…。
経験したことのない状況を想像すると、誰だって怖さを感じるものです。
具体的に何が行われるのか、どんな感覚なのかが分からないからこそ、悪い方へ悪い方へと考えてしまいがちになります。
次に、「痛みへの恐れ」も強い不安の原因です。
「手術中や手術後に、どれくらい痛いのかな?」
「痛み止めはちゃんと効くのかな?」
痛みに対する心配は、非常に現実的で切実な悩みといえます。
特に、過去に強い痛みを経験したことがある方は、より不安を感じやすいかもしれません。



そうですね、「体への影響や変化への不安」も無視できません。
手術によって体に傷が残ること。
一時的に体力が落ちたり、生活に制限が出たりすること。
場合によっては、後遺症が残る可能性もゼロではありません。
自分の体が以前とは変わってしまうかもしれない、という考えは、大きなストレスになりますね。
さらに、「手術がうまくいかなかったらどうしよう」という失敗への恐れ。
「仕事や家庭はどうなるんだろう」といった社会生活への影響。
こうした様々な要因が絡み合って、手術前の不安は形作られています。



まずは、「自分は今、こういう理由で不安なんだな」と客観的に受け止めてみましょう。
それだけでも、少し心が落ち着くことがあります。
次のステップとして、それぞれの不安に対して、正しい情報を集め、具体的な対策を考えていくことが大切です。
この後、その具体的な方法を一緒に見ていきましょうね。
開腹手術と腹腔鏡手術、どう違う?特徴と選び方のポイント


あなたが行う手術は、「開腹手術」ですか?それとも「腹腔鏡手術」でしょうか?
医師から説明はあったと思いますが、改めてそれぞれの特徴を知っておくと、ご自身の状況への理解が深まり、漠然とした不安が和らぐことがあります。
「開腹手術」について
これは、お腹をある程度の長さ(数cm~十数cm以上)で切開して、医師が直接目で見て、手を使って行う従来からの手術方法です。
広い視野で患部を確認できるため、
- がんが大きく広がっている可能性がある場合
- 癒着(組織同士がくっついている状態)がひどい場合
- 緊急手術が必要な場合
などに選択されることが多いです。
デメリットとしては、傷が大きくなるため、術後の痛みが比較的強く、回復にも時間がかかる傾向があります。
また、傷跡が目立ちやすいという点も挙げられます。
「腹腔鏡手術(ふくくうきょうしゅじゅつ)」について
こちらは、お腹に数カ所、小さな穴(5mm~12mm程度)を開けて、そこから「腹腔鏡」というカメラと、細長い手術器具(鉗子:かんし)を挿入して行う手術です。
医師はモニターに映し出される拡大された映像を見ながら、器具を操作して手術を進めます。
メリットは、なんといっても傷が小さく目立たないこと。
そして、術後の痛みが比較的少なく、回復が早い傾向にあることです。
入院期間も短くなることが多いですね。
ただし、すべての手術が腹腔鏡で行えるわけではありません。
高度な技術が必要なため、執刀医の経験が重要になりますし、手術時間も開腹手術より長くなることがあります。
また、手術中に予期せぬ出血があった場合などには、安全のために開腹手術に切り替わる可能性もあります。






どちらの手術方法にも、メリットとデメリットがあります。
大切なのは、ご自身の状況に合わせて最適な方法が選択されていると理解すること。
そして、その手術方法の特性を知った上で、術後の経過などをイメージしておくことです。
分からないことは、ぜひ主治医や看護師さんに質問して、疑問を解消しておきましょうね。
【体験談紹介】先輩患者はどう乗り越えた?不安解消のヒント


「他の人は、どんなふうに手術前の不安を乗り越えたんだろう?」
そう思うのは自然なことです。
実際に手術を経験した方の声は、何よりの安心材料になったり、具体的なヒントを与えてくれたりします。
ここでは、いくつか体験談(架空の事例を含む)をご紹介しましょう。
Aさん(40代女性・腹腔鏡手術)の場合:
「初めての手術で、とにかく痛みが怖かったです。でも、看護師さんが『痛かったらすぐ言ってくださいね。我慢しないでください』と何度も言ってくれて。手術後も、痛み止めの点滴や飲み薬で、想像していたよりずっと楽でした。不安だったことは、事前に質問リストを作って先生に全部聞きました。疑問が解消されたのが大きかったですね。」
Bさん(60代男性・開腹手術)の場合:
「自営業なので、仕事のことが一番の心配でした。入院前に、従業員としっかり打ち合わせをして、緊急連絡網も作っておきました。術後は思ったより回復に時間がかかりましたが、『今は体を治すのが仕事』と割り切って、無理せずリハビリに専念。家族のサポートもありがたかったです。事前に不安を共有しておいて良かったと思います。」



Cさん(50代女性・腹腔鏡手術)の場合:
「インターネットで体験談を読み漁って、逆に不安が増してしまった時期がありました。怖い情報ばかり目についてしまって…。でも、信頼できる病院のサイトや、公的な医療情報を見るようにしたら、落ち着きました。あとは、好きな音楽を聴いたり、編み物をしたり、気を紛らわせる時間を作ることも意識しましたね。」
Dさん(70代男性・開腹手術)の場合:
「手術そのものより、麻酔からちゃんと覚めるのかが心配でした。麻酔科の先生が事前に丁寧に説明してくれて、『お任せください』と言ってくれたのが心強かったです。術後は、早く体を動かした方が回復が早いと聞いて、痛くても少しずつ歩く練習を頑張りました。目標を持つことが大事だと感じましたね。」



これらの体験談から見えてくるヒントは、
- 痛みを過度に恐れず、対策があることを知る
- 疑問や不安は、遠慮なく医療スタッフに伝える
- 信頼できる情報源を選ぶ
- 仕事や生活のことは、事前に段取りをつけておく
- 家族や周囲のサポートを頼る
- 気分転換やリラックスできることを見つける
- 回復に向けて、小さな目標を持つ
といったことでしょうか。
完璧に不安をなくすことは難しいかもしれません。
でも、先輩たちの経験を参考に、あなたなりの「安心の準備」を進めていきましょう。
「自分もきっと乗り越えられる」そう思えることが、大きな力になりますよ。
手術の痛み、どのくらい?最新の痛みの管理(ペインコントロール)とは


手術を控えて、多くの方が最も心配されるのが「痛み」についてではないでしょうか。
「どれくらい痛いのかな…」「痛みに耐えられるかな…」そんな不安でいっぱいかもしれませんね。
でも、安心してください。
現代の医療では、手術に伴う痛みをできる限り和らげるための様々な工夫(ペインコントロール)が進んでいます。
まず、手術中の痛みについて。
全身麻酔の場合は、手術中は完全に意識がなく、痛みを感じることはありません。
部分的な麻酔(硬膜外麻酔や脊髄くも膜下麻酔など)の場合も、手術する部位の感覚はなくなっているので、痛みを感じることはありません。
「手術中に目が覚めたらどうしよう…」と心配される方もいますが、麻酔科医が常に状態を監視しているので、まず心配いりませんよ。



確かに、手術が終わって麻酔が覚めてくると、傷の痛みが出てきます。
痛みの程度は、手術の種類(開腹か腹腔鏡か)、手術の部位、個人の感じ方によって差があります。
一般的には、開腹手術の方が腹腔鏡手術よりも術後の痛みは強い傾向にありますが、これも個人差が大きいです。



術後の痛みを和らげる主な方法には、以下のようなものがあります。
- 点滴からの鎮痛剤: 手術直後から、痛みの状態に合わせて点滴で鎮痛剤を投与します。
- 飲み薬・座薬の鎮痛剤: 痛みの程度に応じて、定期的に、あるいは痛い時に飲む薬や座薬を使います。
- 硬膜外麻酔(こうまくがいまし): 背中から細いチューブを入れて、そこから継続的に麻酔薬を注入し、手術部位周辺の痛みを和らげる方法です。特に開腹手術後などに有効です。自分で痛みの強さに合わせて薬の量を調整できるPCA(自己調節鎮痛法)ポンプを使うこともあります。
- 神経ブロック: 特定の神経の近くに麻酔薬を注射して、その神経が支配する範囲の痛みを抑える方法です。
これらの方法を単独で、あるいは組み合わせて使うことで、術後の痛みを最小限に抑えることが可能になっています。
大切なのは、「痛みを我慢しないこと」です。
痛みを我慢していると、
- 体が緊張して血圧が上がったり、心臓に負担がかかったりする
- 呼吸が浅くなり、肺炎などの合併症のリスクが高まる
- 痛みのために体を動かせず、回復が遅れる
- 痛みの記憶が残り、慢性的な痛みにつながることもある
といったデメリットがあります。



最新のペインコントロールについて理解し、「痛みをコントロールできるんだ」と知るだけでも、不安はかなり軽くなるはずです。
もし痛みについて特に心配なことがあれば、手術前の診察で医師や麻酔科医にしっかり伝えておきましょう。
麻酔は大丈夫?知っておきたい麻酔の種類と流れ


「麻酔って、なんだか怖い…」
「ちゃんと目が覚めるのかな?」
手術そのものと同じくらい、麻酔に対して不安を感じる方も少なくありません。
麻酔は、安全に手術を行うために不可欠なものです。
種類や流れを知っておくことで、漠然とした不安を減らすことができますよ。
手術で使われる麻酔は、大きく分けて「全身麻酔」と「局所麻酔」があります。
どちらの方法が選択されるかは、手術の種類、場所、時間、そして患者さんの体の状態によって決まります。
【全身麻酔】
これは、意識と全身の感覚をなくす麻酔方法です。
お腹の手術(開腹・腹腔鏡)では、多くの場合、全身麻酔が用いられます。
- 流れ:
- 点滴から麻酔薬を入れたり、マスクから麻酔ガスを吸ったりすると、数秒~数十秒で眠りに入ります。
- 眠った後、呼吸を助けるために口から喉へチューブ(気管チューブ)を入れることがあります。
- 手術中は、麻酔科医が心拍数、血圧、呼吸、体温などを常に監視し、麻酔の深さを適切に調節しています。
- 手術が終わると麻酔薬の投与を中止し、しばらくすると自然に目が覚めます。
- 特徴: 手術中の記憶や痛みは全くありません。完全に意識がない状態で手術を受けられます。






【局所麻酔】
これは、体の一部分の感覚だけをなくす麻酔方法です。意識は保たれたままです。
お腹の手術で単独で行われることは少ないですが、全身麻酔と組み合わせて痛みの管理に使われることがあります(例:硬膜外麻酔、脊髄くも膜下麻酔)。
- 硬膜外麻酔(こうまくがいまし): 前の章でも触れましたが、背骨の近くにある硬膜の外側に麻酔薬を注入し、お腹や胸、足などの広範囲の痛みを和らげます。術後の痛みのコントロールによく使われます。
- 脊髄くも膜下麻酔(せきずいくもまくかまし): 硬膜よりもさらに内側の脊髄液の中に麻酔薬を注入します。下半身の手術などで使われることがあります。
麻酔を担当するのは、「麻酔科医」という専門の医師です。
麻酔科医は、手術前に患者さんの健康状態を詳しくチェックし、最も安全な麻酔方法を選択します。
手術中も常に患者さんのそばにいて、全身の状態を管理し、安全を守っています。
もし、麻酔に関して疑問や不安な点があれば、手術前の麻酔科医の説明の際に、遠慮なく質問しましょう。
例えば、
- 以前に麻酔で気分が悪くなったことがある
- アレルギー体質である
- 現在飲んでいる薬がある
といった情報は、必ず伝えるようにしてください。
麻酔の専門家である麻酔科医が、あなたの不安に丁寧に答えてくれるはずです。
麻酔の仕組みと安全管理体制を知ることで、「安心して任せられる」と思えるようになるでしょう。
【具体的ステップ】手術前の不安を解消する7つの方法


さて、ここからは、手術前の不安を具体的に解消していくための行動プランをご紹介します。
「何をすればいいか分からない」という状態から、「これをやってみよう!」と思えるようになるはずですよ。
ぜひ、できそうなことから試してみてくださいね。
ステップ1:信頼できる情報を集める
不安の多くは「知らないこと」から生まれます。
ただし、やみくもにネット検索すると、不確かな情報やネガティブな体験談に惑わされることも。
- 担当の医師や看護師に直接質問する
- 病院が提供しているパンフレットや資料を読む
- 公的機関(国立がん研究センターなど)や学会のウェブサイトを見る
など、信頼できる情報源を選びましょう。
正しい知識は、漠然とした不安を具体的な理解に変えてくれます。
ステップ2:手術や回復の過程をイメージする
医師の説明や体験談などを参考に、手術当日の流れや、術後の回復がどのように進んでいくのかを具体的にイメージしてみましょう。
「手術室に入って、麻酔がかかって、目が覚めたら病室にいる」「最初は痛いけど、痛み止めで楽になる」「少しずつ歩けるようになって、食事が始まって…」
良いイメージを持つことで、前向きな気持ちが生まれやすくなります。
ステップ3:リラックスできる方法を見つける
不安で心が張り詰めている時は、意識的にリラックスする時間を作りましょう。
- 深呼吸: ゆっくり息を吸って、長く吐く腹式呼吸は、自律神経を整え、心を落ち着かせる効果があります。
- 好きな音楽を聴く: 心地よい音楽は、気分転換に役立ちます。
- 軽いストレッチや散歩: 体を動かすことで、気分もスッキリします。(医師に確認の上で行いましょう)
- 趣味に没頭する: 編み物、読書、映画鑑賞など、集中できる好きなことに時間を使うのも良い方法です。



ステップ4:不安な気持ちを言葉にする・相談する
一人で抱え込まず、信頼できる人に気持ちを話してみましょう。
- 家族や親しい友人: 心配事を共有するだけでも、気持ちが楽になります。
- 医師や看護師: 専門的な視点からのアドバイスや、安心できる言葉がもらえます。
- 同じ経験をした人: 共感し合えたり、具体的なアドバイスが得られたりします。(ただし、比較しすぎないように注意)
ステップ5:入院や術後の生活に必要な準備をする
身の回りのことを整えておくことも、心の安定につながります。
入院に必要なものを揃えたり、退院後の生活(家事、仕事など)について家族と話し合ったり、具体的な準備を進めることで、「やるべきことをやっている」という安心感が得られます。準備リストについては、次の章で詳しくお伝えしますね。
ステップ6:体調を整える
手術に向けて、できる範囲で体調を整えておくことも大切です。
- バランスの取れた食事: 栄養をしっかり摂りましょう。
- 十分な睡眠: 質の良い睡眠は、心と体の回復力を高めます。
- 禁煙・節酒: 喫煙は傷の治りを遅らせたり、術後の合併症のリスクを高めたりします。禁煙は必須です。飲酒も控えましょう。



ステップ7:ポジティブな側面に目を向ける
手術は怖いかもしれませんが、病気を治し、健康を取り戻すためのポジティブなステップでもあります。
「手術が終われば、あの症状から解放される」
「元気になったら、〇〇をしたい」
手術の先にある、より良い未来を想像してみましょう。
これらのステップをすべて完璧に行う必要はありません。
あなたにとって「これならできそう」「これをやると少し楽になるかも」と思えるものを、一つでも二つでも試してみてください。
小さな行動の積み重ねが、大きな安心感へと繋がっていきますよ。
入院生活・術後の回復をスムーズにするための準備リスト


手術に向けて心の準備が進んだら、次は具体的な「モノ」と「コト」の準備に取り掛かりましょう。
事前にしっかり準備しておくことで、入院中の不便さを減らし、退院後の生活もスムーズにスタートできます。
ここでは、一般的な準備リストをご紹介しますが、ご自身の状況に合わせて調整してくださいね。
【入院時に必要なモノ】
□ 書類・貴重品関連
□ 健康保険証、各種医療証
□ 診察券
□ 入院申込書、保証書などの病院指定書類
□ 印鑑
□ 現金(売店利用など、必要最低限に)
□ クレジットカードやキャッシュカード
□ お薬手帳(普段飲んでいる薬がある場合)
□ 衣類関連
□ 前開きのパジャマ(2~3組):術後は着替えやすい前開きが便利
□ 下着(多めに):洗濯が難しい場合も考慮
□ 靴下(滑りにくいもの):転倒防止
□ カーディガンや羽織るもの:体温調節に
□ 退院時の服
□ 洗面・衛生用品
□ 歯ブラシ、歯磨き粉、コップ
□ シャンプー、リンス、ボディソープ
□ タオル(バスタオル、フェイスタオルを複数枚)
□ 洗顔料、化粧水などの基礎化粧品
□ ティッシュペーパー、ウェットティッシュ
□ 生理用品(女性の場合)
□ 爪切り、ヘアブラシ、鏡
□ 食事関連
□ 蓋つきのコップまたはタンブラー
□ 割りばし、スプーン、フォーク(病院で用意されるか確認)
□ ストロー(寝たまま飲むのに便利)
□ ふりかけ、お茶漬けの素など(食欲がない時用に)※持ち込み可能か確認
□ その他
□ 履き慣れた室内履き(滑りにくく、着脱しやすいもの)
□ スマートフォン、充電器、イヤホン
□ 筆記用具、メモ帳
□ 本、雑誌、ゲーム機など暇つぶしグッズ
□ 小さめのバッグ(院内移動用)
□ マスク(予備も)
□ S字フック(ベッドサイドに小物を掛けるのに便利)
□ 時計(腕時計や置き時計)






【術後の回復を助けるモノ(あると便利なもの)】
□ 腹帯(ふくたい)または術後用ガードル: 傷を保護し、お腹を支えて痛みを和らげる効果が期待できます。(医師の指示に従いましょう)
□ クッション: 座る時や寝る時に、楽な姿勢をとるのに役立ちます。
□ 着圧ソックス: 血栓予防のために推奨されることがあります。
□ 楽なワンピースやウエストゴムのズボン: 退院後の服装として。
【事前にやっておくコト】
□ 家族や職場への連絡・相談:
* 入院期間、手術日、連絡先を伝える
* 緊急連絡先を確認する
* 家事の分担や子供の世話などを相談・依頼する
* 仕事の引き継ぎ、休業の手続きを行う
□ 公的・民間サービスの確認・手配:
* 高額療養費制度の申請(限度額適用認定証の取得)
* 生命保険の給付金請求の準備
* 必要であれば、家事代行サービスや宅配サービスの検討
□ 自宅の準備:
* 掃除や片付け
* 日用品や食料品の買い置き
* 退院後、体を休めやすい環境を整える(布団の準備など)
□ 医療スタッフとの最終確認:
* 手術や麻酔に関する最終的な疑問点の解消
* アレルギーや常用薬についての再確認



完璧を目指す必要はありませんが、事前にできることを済ませておくことで、入院生活や退院後の回復期をより心穏やかに、そしてスムーズに過ごすことができますよ。
医師・看護師との上手なコミュニケーション術|疑問や不安を伝えるコツ


手術を安心して受けるためには、医療スタッフとの信頼関係がとても重要です。
疑問や不安を抱えたままにせず、上手にコミュニケーションをとることで、納得して治療に臨むことができます。
「でも、先生は忙しそうだし、聞きにくいな…」と感じる方もいるかもしれませんね。
ここでは、スムーズなコミュニケーションのためのコツをお伝えします。
コツ1:聞きたいこと・伝えたいことをメモにまとめる
診察や説明の場では、緊張してしまって聞きたかったことを忘れてしまう、ということはよくあります。
事前に、
- 疑問点: 手術の方法、リスク、麻酔、術後の経過など、分からないこと。
- 不安なこと: 痛み、副作用、仕事復帰など、心配な気持ち。
- 自分の状況: アレルギー、既往歴、常用薬、体調の変化など、伝えておくべき情報。
- 希望: 痛みのコントロール方法、術後のケアなど、自分の希望があれば。
これらを箇条書きでメモしておきましょう。
メモを見ながら話せば、聞き忘れや伝え漏れを防げます。



コツ2:質問するタイミングを見計らう
医師は外来や手術で忙しいことが多いですが、質問してはいけないわけではありません。
- 診察時: メモを見ながら、要点を絞って質問しましょう。
- 入院中の回診時: 医師が病室に来たタイミングで質問できます。事前に看護師に「先生に聞きたいことがある」と伝えておくのも良いでしょう。
- 看護師に相談する: 医師に直接聞きにくいことや、日々のケアに関する疑問は、まず看護師さんに相談してみましょう。医師に確認が必要な場合は、繋いでくれたり、代わりに聞いてくれたりします。
- 説明の時間をもらう: もし、じっくり話を聞きたい場合は、「〇〇について詳しくお聞きしたいので、少しお時間をいただけますか?」とお願いしてみるのも一つの方法です。
コツ3:具体的に、正直に伝える
「なんとなく不安なんです」というよりは、「手術後の痛みがどのくらい続くのか不安です」「〇〇という副作用が心配です」のように、具体的に伝える方が、相手も的確に答えやすくなります。
また、心配な気持ちや、体調の変化なども正直に伝えることが大切です。
遠慮して我慢してしまうと、適切な対応が遅れてしまう可能性もあります。
コツ4:説明を理解できたか確認する
専門用語が多くて、一度の説明では理解できないこともあります。
そんな時は、遠慮せずに聞き返しましょう。
「すみません、今の〇〇という部分がよく分からなかったので、もう一度説明していただけますか?」
「つまり、〇〇ということでしょうか?」
など、自分の言葉で確認すると、理解が深まります。
説明された内容をメモするのも良い方法です。



コツ5:家族に同席してもらう
もし可能であれば、説明を聞く際に家族に同席してもらうのも良いでしょう。
一人で聞くよりも、客観的に話を聞けたり、聞き忘れたことを補ってもらえたりします。
また、精神的な支えにもなりますね。
上手なコミュニケーションは、信頼関係の土台です。
医療スタッフを「治療のパートナー」と考え、積極的に関わっていくことで、不安は軽減され、より安心して手術に臨むことができますよ。
家族や周囲のサポートを上手に受け入れるには?


手術という大きな出来事を乗り越えるためには、家族や友人など、周りの人のサポートが大きな力になります。
でも、中には「迷惑をかけたくない」「心配させたくない」と、頼ることに遠慮してしまう方もいるかもしれませんね。
しかし、こんな時こそ、上手に周りを頼ることも大切なのです。
まず、自分の状況と気持ちを正直に伝えることから始めましょう。
「今度、〇〇の手術を受けることになったんだ。正直、すごく不安で…」
「入院中は、〇〇をお願いできないかな?」
具体的に伝えることで、周りの人も何をサポートすれば良いのかが分かりやすくなります。
心配させたくない、という気持ちも分かりますが、何も言わない方がかえって心配をかけてしまうこともありますよ。






サポートをお願いする時は、できるだけ具体的に伝えましょう。
「洗濯物を取りに来てほしい」「退院時に迎えに来てほしい」「上の子の送り迎えをお願いしたい」など、具体的な方が相手も動きやすいです。
一度にたくさんのことを頼むのではなく、「これだけお願いできる?」と、相手の負担にならない範囲でお願いするのもポイントです。
そして、サポートしてもらったら、必ず感謝の気持ちを伝えましょう。
「ありがとう、本当に助かったよ」
「おかげで安心して療養できる」
感謝の言葉は、相手にとっても嬉しいものですし、良好な関係を保つ上でとても大切です。
また、「甘える練習」も必要かもしれません。
特に、普段しっかりしている方や、周りの世話をすることが多い方は、人に頼ることに慣れていない場合があります。
でも、今はあなたの体を治すことが最優先。
「今は頼って良い時期なんだ」と自分に言い聞かせ、周りのサポートをありがたく受け入れましょう。
弱音を吐ける相手がいる、というだけでも心強いものです。
一方で、家族側の心構えも大切です。
患者さんの不安な気持ちに寄り添い、話を聞いてあげることがまず第一です。
そして、過度に心配しすぎず、患者さんが安心して治療に専念できるような環境を作ってあげましょう。
具体的なサポートを申し出るだけでなく、「何かできることがあったら言ってね」と、いつでも頼れる姿勢を示すことも大切です。



困ったときはお互い様です。
周りのサポートを上手に受け入れることで、心身の負担が軽くなり、回復もきっと早まりますよ。
【Q&A】手術前のよくある質問と回答


最後に、手術を控えた方がよく疑問に思うこと、心配されることについて、Q&A形式でお答えします。
ここにない疑問や、もっと詳しく知りたいことは、遠慮なく主治医や看護師さんに質問してくださいね。
Q1. 手術前に食事制限はありますか?
A1. はい、多くの場合あります。安全に麻酔を行うため、手術前日の夕食後から絶食、手術当日は水分も禁止(絶飲)となるのが一般的です。胃の中に食べ物や飲み物が残っていると、麻酔中に吐いてしまい、それが気管に入って肺炎(誤嚥性肺炎)を起こす危険があるためです。具体的な時間や内容は、医師や看護師の指示に必ず従ってください。



Q2. 手術前に運動はしても良いですか?
A2. 過度な運動は避けるべきですが、軽い散歩など、普段通りの適度な運動であれば問題ないことが多いです。むしろ、体力を維持しておくことは、術後の回復に役立ちます。ただし、病状によっては運動が制限される場合もありますので、必ず医師に確認してから行うようにしましょう。
Q3. 手術の傷跡はどのくらい残りますか?
A3. 傷跡の大きさや残り方は、手術の種類(開腹か腹腔鏡か)、切開した場所、個人の体質(ケロイド体質など)によって大きく異なります。
- 開腹手術: 切開した長さの線状の傷跡が残ります。
- 腹腔鏡手術: 数カ所の小さな点状の傷跡になります。
最近は、傷が目立ちにくくなるような縫合方法や、術後のケア(テーピングなど)も進歩しています。傷跡が心配な場合は、形成外科的な配慮が可能かなど、事前に医師に相談してみるのも良いでしょう。
Q4. 手術後、どのくらいで仕事に復帰できますか?
A4. これも手術の種類、回復の程度、そして仕事の内容(デスクワークか、体を動かす仕事かなど)によって大きく異なります。
- 腹腔鏡手術: 早ければ術後1~2週間程度でデスクワークなら復帰可能な場合もあります。
- 開腹手術: 一般的にはもう少し時間がかかり、術後1ヶ月~数ヶ月程度を目安とすることが多いです。
焦らず、ご自身の体調と相談しながら、医師の許可を得て復帰時期を決めることが大切です。職場とも事前に相談しておきましょう。



Q5. 手術や入院にかかる費用はどのくらいですか? 高額療養費制度って何ですか?
A5. 手術費用は、手術の種類、入院期間、個室利用の有無などによって大きく変動します。ただし、日本には「高額療養費制度」というものがあります。これは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。年齢や所得によって上限額は異なります。以前ですと事前に「限度額適用認定証」を入手しておけば、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができたのですが、限度額適用認定証(2024年12月2日以降、限度額適用認定証は新たに発行されなくなります)
その代わりマイナ保険証を利用すると、限度額認定証などがなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。加入している健康保険(協会けんぽ、組合健保、国民健康保険など)の窓口に申請しましょう。また、民間の医療保険に加入している場合は、給付金が受け取れるか確認しておきましょう。



Q6. 術後の痛みはいつまで続きますか?
A6. 痛みのピークは、一般的に手術当日~術後2、3日程度ですが、その後も鈍い痛みや、動いた時の痛みがしばらく続くことがあります。個人差が大きいですが、鎮痛剤を使いながら、徐々に楽になっていくのが一般的です。痛みが長引く場合や、急に強くなった場合は、我慢せずに医師や看護師に相談してください。
これらのQ&Aが、あなたの疑問や不安を少しでも解消する手助けになれば幸いです。
繰り返しになりますが、一人で悩まず、分からないこと、心配なことは、必ず医療スタッフに相談してくださいね。
安心して手術の日を迎えられるよう、心から応援しています。